feets blog
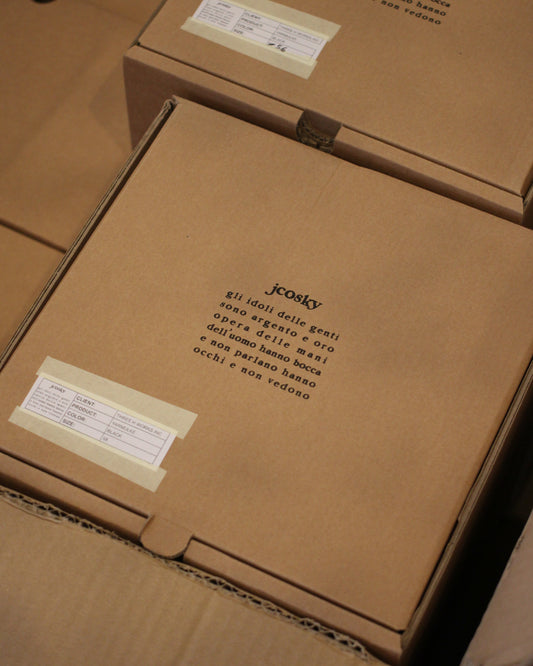



KIJIMA TAKAYUKI 24SS Vol.1
いつもfeetsをご愛顧いただき誠にありがとうございます。feetsの小林です。すがすがしい初夏の季節となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか?
KIJIMA TAKAYUKI 24SS Vol.1
いつもfeetsをご愛顧いただき誠にありがとうございます。feetsの小林です。すがすがしい初夏の季節となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか?
アントワープからの使者
かなり寒くなってきましたね。 軽快なステップで暖を取る、小坂です。 23AW Howlin'のデリバリーが、ベルギーから到着致しました。 そもそもHowlin'(ハウリン)ってどんなブランド? ということでざっと説明していきましょう。 Howlin'はベルギーはアントワープに拠点を置くニットウェアブランドです。 ベルギーで1980年代に始まった「ニュービート」というエレクトロニックミュージックのジャンルからデザインのインスピレーションを得ているブランドです。 その為、Howlin'の作るアイテムはポップでキュートなモノばかり。 生産は、主にベルギー、スコットランド、アイルランドで行われています。 彼らが心掛けていることは、職人による手工芸を守ること、そして現代のスピード重視の風潮や機械化を求める社会においてゆっくりと作業を進めることによる丁寧なものづくり、大切にされているブランドです。 彼らはそれを「小さなレコード会社が、解説文付きで、お手製のスタンプが押された7インチレコードを作るように。」と例えています。 良い表現ですね…。 やはり伝統のある工場さんの為、Howlin'らしいユニークなデザインのものを提案すると、最初は怪訝な顔をされたそうですが、今は喜んで作ってくれるそうです。 伝統と新しいカルチャーの融合が非常に良い塩梅となっていて、手作業という点においてHowlin'のプロダクトからはどこか温もりを感じるのです。 またHowlin'の… おっと。 長くなってしまいそうなので、そんなHowlin'のアイテムをざっと紹介していきましょう。 まず最初に "Best Walrus In Town" セイウチが氷山の上に佇んでいるニット。 直訳すると、「町で一番のセイウチ」(笑) ちょっと焦点が合ってないマヌケな表情が愛くるしいですね。 アウターの隙間からセイウチがチラッと見えるのも想像するだけで良いですね。 お色は"Blue"と"Grey"の2色ございます。 つぎに "Taste...
アントワープからの使者
かなり寒くなってきましたね。 軽快なステップで暖を取る、小坂です。 23AW Howlin'のデリバリーが、ベルギーから到着致しました。 そもそもHowlin'(ハウリン)ってどんなブランド? ということでざっと説明していきましょう。 Howlin'はベルギーはアントワープに拠点を置くニットウェアブランドです。 ベルギーで1980年代に始まった「ニュービート」というエレクトロニックミュージックのジャンルからデザインのインスピレーションを得ているブランドです。 その為、Howlin'の作るアイテムはポップでキュートなモノばかり。 生産は、主にベルギー、スコットランド、アイルランドで行われています。 彼らが心掛けていることは、職人による手工芸を守ること、そして現代のスピード重視の風潮や機械化を求める社会においてゆっくりと作業を進めることによる丁寧なものづくり、大切にされているブランドです。 彼らはそれを「小さなレコード会社が、解説文付きで、お手製のスタンプが押された7インチレコードを作るように。」と例えています。 良い表現ですね…。 やはり伝統のある工場さんの為、Howlin'らしいユニークなデザインのものを提案すると、最初は怪訝な顔をされたそうですが、今は喜んで作ってくれるそうです。 伝統と新しいカルチャーの融合が非常に良い塩梅となっていて、手作業という点においてHowlin'のプロダクトからはどこか温もりを感じるのです。 またHowlin'の… おっと。 長くなってしまいそうなので、そんなHowlin'のアイテムをざっと紹介していきましょう。 まず最初に "Best Walrus In Town" セイウチが氷山の上に佇んでいるニット。 直訳すると、「町で一番のセイウチ」(笑) ちょっと焦点が合ってないマヌケな表情が愛くるしいですね。 アウターの隙間からセイウチがチラッと見えるのも想像するだけで良いですね。 お色は"Blue"と"Grey"の2色ございます。 つぎに "Taste...
普遍的な美
心地良い風、秋、最高です。コーヒーもお酒も美味しい、そんな季節です。小坂です。さて、今年もアルペンの時期がやって参りました。 生地、縫製など、全ての生産工程をフランスで完結させる拘り抜いた”MADE IN FRANCE”の洋服。 あくまで販売する身ですが、服を消費する立場としても、生産国に拘りすぎるのも近年はあまりよろしくない事かとは思いますが、やはり高揚感を覚えてしまいます。 フランス人のローランとマークの従兄弟2人が作る洋服は、まさにフランスの日常着、"リアル・クローズ"。 これを書いている約2ヶ月前、マークがfeetsに来てくれて、1時間程お話をしました。 ローランもマークも古着やヴィンテージクロージングが好きな方で、少し余計で、考え尽くされていないようなデザインが好きとのことでした。 良い意味でデザインが削ぎ落とされ過ぎていない服に、魅力を感じるのです。そこに自分の色を如何に足すかを考えるのが非常に楽しいのです。ざっとアイテムのご紹介をしましょう。 こちらは"LOFT V"フランスでは盛んなセーリングのウェアをデザインベースに。PRIMALOFTという人工羽毛を使用。1980年代初頭、スペースシャトルの断熱材を製造していたアメリカのALBANY社という会社に、アメリカ国軍が依頼を出し、開発した超微細なマイクロファイバー素材です。なんとこの素材、洗えます。←(ここ重要)洗えるアウターです。 袖付きの"LOFT J"結構印象変わりますね、こちらも格好良い。 "CONTOUR"程よい肉感のモヘアとウール。軽くてしっかり暖かい。ポケットの形も良いです。 "PLANO"メリノウールを使用した畦編みニット。ガッシリとしながらも、伸縮性がある為、軽やかな着心地。 "DYCE"裾のロールが愛くるしいニット。メリノウールをロールさせ、カットソーのようなシルエットに。小坂も微笑んでしまいますね。ARPENTEURのニットは毛玉が出来ないそうです!(前バイヤーの証言)僕も買って試そうかなあと思っております、、、。。普遍的って美しい。サイズ、色欠け、早くも出てきております。3連休ということで是非、祐天寺に遊びに来てください。「普遍的な美」
普遍的な美
心地良い風、秋、最高です。コーヒーもお酒も美味しい、そんな季節です。小坂です。さて、今年もアルペンの時期がやって参りました。 生地、縫製など、全ての生産工程をフランスで完結させる拘り抜いた”MADE IN FRANCE”の洋服。 あくまで販売する身ですが、服を消費する立場としても、生産国に拘りすぎるのも近年はあまりよろしくない事かとは思いますが、やはり高揚感を覚えてしまいます。 フランス人のローランとマークの従兄弟2人が作る洋服は、まさにフランスの日常着、"リアル・クローズ"。 これを書いている約2ヶ月前、マークがfeetsに来てくれて、1時間程お話をしました。 ローランもマークも古着やヴィンテージクロージングが好きな方で、少し余計で、考え尽くされていないようなデザインが好きとのことでした。 良い意味でデザインが削ぎ落とされ過ぎていない服に、魅力を感じるのです。そこに自分の色を如何に足すかを考えるのが非常に楽しいのです。ざっとアイテムのご紹介をしましょう。 こちらは"LOFT V"フランスでは盛んなセーリングのウェアをデザインベースに。PRIMALOFTという人工羽毛を使用。1980年代初頭、スペースシャトルの断熱材を製造していたアメリカのALBANY社という会社に、アメリカ国軍が依頼を出し、開発した超微細なマイクロファイバー素材です。なんとこの素材、洗えます。←(ここ重要)洗えるアウターです。 袖付きの"LOFT J"結構印象変わりますね、こちらも格好良い。 "CONTOUR"程よい肉感のモヘアとウール。軽くてしっかり暖かい。ポケットの形も良いです。 "PLANO"メリノウールを使用した畦編みニット。ガッシリとしながらも、伸縮性がある為、軽やかな着心地。 "DYCE"裾のロールが愛くるしいニット。メリノウールをロールさせ、カットソーのようなシルエットに。小坂も微笑んでしまいますね。ARPENTEURのニットは毛玉が出来ないそうです!(前バイヤーの証言)僕も買って試そうかなあと思っております、、、。。普遍的って美しい。サイズ、色欠け、早くも出てきております。3連休ということで是非、祐天寺に遊びに来てください。「普遍的な美」

kearnyとセルロイド

feets exclusive pants

Styling with On 前編

MATSUFUJI trousers

普遍的にイイもの
